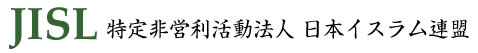2010年後半から燃え始めたアラブの春革命は、2011年幾つかのアラブの体制を打倒して今日に到る。その後を追う国もあるが、昨今のアラブ諸国の動き次第では、その動きにストップがかかるかもしれない。
アラブの春革命が起こったことによって誕生した、何人かの新大統領たちは、今回の預言者ムハンマド冒涜映画に対する対応で、彼らの能力の限界を、示してしまったのではないか。
対応を間違えた人物の典型が、エジプトのモルシー大統領であろう。彼の出身母体はムスリム同胞団という、イスラム原理主義組織だ。当然のことながら、ムスリム同胞団はエジプトを始め、アラブ各国で異常なまでの拒否反応を、この映画に示している。
エジプトのムスリム同胞団は、激しい抗議の立場を示し、デモを煽っているのだ。その流れのなかで、モルシー大統領はアメリカ大使館が、デモ隊によって襲撃され、破壊されたことに対して陳謝するよりも、預言者ムハンマド冒涜映画に対する、非難を先にしたのだ。そして、アメリカに対する軽い謝罪が、その後、大分時間が経過してから、行われている。
チュニジアでもほぼ同じ展開であったし、スーダンでもイエメンでも同様だ。そうしたなかで、最も早くアメリカに対し、詫びを入れたのがリビアだった。それは当然であろう。映画を作ったのはアメリカ政府ではないのだから。
アメリカ大使館に抗議をすることによって、映画への抗議をアメリカ側に伝えることは許されても、アメリカ大使館破壊は、筋の通らない話であろう。
トルコはアラブの春革命に加わった国ではないが、トルコの与党公正発展党(AKP)が、宗教的色彩の強い政党であるためか、エルドアン首相はアラブの春諸国の大統領たちと、同じ様な反応を預言者ムハンマド冒涜映画に対して、示している。
本来であれば宗教と政治とのバランスを、うまく創り上げたトルコの与党は、今回のようなイスラム諸国で起こっている騒乱で、しかるべき指導力を発揮すべきではなかったのか。
結局のところ、アラブの春革命を起こした国と、そのリーダーたちは押しなべて、イスラム原理主義的な過激な、対応を示すことになった。そのことは非イスラム世界からの信頼を、完全に失わせることになるのではないか。
同時に、そうした短慮な指導者に導かれる体制を、一日も早く打倒しようという国内外の勢力が、元気付くのではないか。かの地ではいま『アラブの春』は過ぎ、『アラブの秋』が始まっているのであろう。