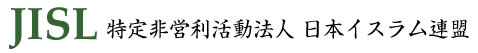アラブ諸国との関係が出来てから、もう40年以上も歳月が過ぎているが、その中でつくづく思うのは、アラブ人とは多くの異なった要素を持つ人たちで構成されており、人くくりには出来ない人たちだということだ。
彼らは人種、宗教、宗派、部族、所得、教育格差など多くの異なる要素を持ち、それぞれが別々の存在だと感じているということだ。その国民を一つにするためには、自国内部からではなく、外部からまとめていき、国民意識を抱かせなければならない、と考えたのはエジプトのナセル大統領だった。
彼はアラブという範囲を設け「君たちはその一部だ」とし、次いで「エジプト国民だ」という意識を持たせていった。そしてそのくくりを強くするためには共通の敵が必要と考え、「イスラエルとユダヤを共通の敵」と定めた。
その共通の敵と戦うためには、アラブ内部の団結が必要であり、忍耐が必要だとも説いた。その団結と忍耐を国民に強要するためには、独裁色が必要だった。結果はうまく行った、鉄の統制が国家を一つにまとめることを、可能にしたのだ。もちろん、その鉄の統制下に反対する者もいたが、大半はそれに従うことによる、安心感を得ることが出来た。
それは共和制王制に関わりなく、アラブ諸国で共通する統治の知恵だった。そのためには「パレスチナ問題支援」、「エルサレムの解放」といったフレーズが価値を持って声高に叫ばれていたのだ。しかし、それはあくまでも道具であって、真の目的ではなかったということだ。
アラブの春革命が始まり、幾つかのアラブ諸国の体制が崩壊すると、アラブ人の本音が出てきている。つまり、アラブは一つなどありえないことであり、パレスチナはアラブ共通の問題ということもありえない、ということになってきているのだ。
それはそれで政治的な、ある種の前進であろうから、歓迎すべきであろう。しかし、そのことによって失ったものは、多すぎはしないかということだ。アラブ諸国、なかでもアメリカによって軍事侵攻されたイラクや、アラブの春革命に見舞われた諸国では、これまで弾圧によって閉じ込められていた、国民の露骨な感情が表面化し、全くまとまりを持ち得ない状態が生まれている。
混乱のなかでは国民の感情が爆発し、暴力が日常を支配するようになっているし、生け贄を求めるようになっている。エジプトのムバーラク大統領に下された『終身刑』に対する反対は『処刑』という血の償いを求めているのだが、それは感情の爆発以外のなにものでもなかろう。
独裁体制を打倒した国民への賞賛の言葉は美しいし、打倒後の感動の瞬間は忘れがたかろうが、その後の混沌と多くの犠牲の排出は何を意味するのか。国民はその結果何を得るのか、その独裁体制打倒という、革命の果実を手にするまでには何年かかるのか、それを大衆は我慢して待ち続けられるのか、疑問は幾つでも沸いてくる。
イラクはアメリカ軍の軍事侵攻からすでに10年以上の歳月が経過しているが、いまだに毎日何十人という人たちが犠牲になっているし、リビアでは内戦が続いている。チュニジアではイスラム原理主義が台頭し、国民はそれまであった世俗的な雰囲気を、全く味わえなくなっている。
一番文化的レベルが高い国家を自負するエジプトでは、世俗派とイスラム原理主義が真っ向から衝突し、何時内戦に変わっても不思議は無い状態にある。あるいはそれを阻止するために、軍による力の支配が始まるかもしれないのだ。
アラブの春革命が、スンナリと民主的新体制を生み出すなどという幻想は、捨てるべきだ。それよりもアラブの春革命が、今後もアラブ世界に拡大して行き、日本を含む先進諸国がその影響を、真正面から蒙ることになる危険性について、考えておくべきだろう。
50年代から60年代、そして70年代の初めにかけて世界中で起こった革命と、いまのアラブの春革命とは根本的に異質なのだということを、明確に意識すべきであろう。当時の革命にはまがりなりにも、社会主義という雛形があり、それが新体制の受け皿となっていたのだが、いまの革命には雛形など無いのだ。だから混沌は続き血が流れるのだ。それはパンドラの箱の蓋を開けたようなものではないのか。