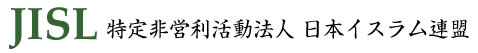過去に何度か指摘してきたことだが、エジプトの選挙ではムスリム同胞団(自由公正党40パーセント)や、サラフィの党(ヌール党25パーセント)が、選挙で好結果を出している。これらの組織はいずれも、イスラム原理主義の組織なのだが、何時の間にかアメリカを先頭に、穏健なイスラム組織のように認識され、宣伝されていた。
日本の朝日新聞もそんな欧米の例に漏れず、ムスリム同胞団は何の危険性も無い、貧民に福祉を行う穏健な宗教団体、という切り口の記事を書き連ねてきている。そこにはムスリム同胞団に対する、何の警戒心も感じられない。
ムスリム同胞団とはそんな甘い組織ではない、とあえて主張したい。そもそ、ムスリム同胞団とは1928年、スエズ運河に近いイスマイリーヤの街で、ハッサン・バンナーという名の学校教師が始めた、対英闘争の組織なのだ。したがって、彼らは武力闘争も辞さないという強硬な考えを、根底に持っているこことを忘れるべきではない。
ムスリム同胞団が一見穏健に見えるようになったのは、エジプトのナセル大統領による、大弾圧の結果であろう。ムスリム同胞団のメンバーはその結果、地下に潜るか外国に逃れ、活動を継続している。
ムスリム同胞団から分派して、強硬武力闘争路線に変わった組織ガマーア・タクフィール・ワ・ヘグラの一員が、サダト大統領を暗殺しているし、他にも要人暗殺や暗殺未遂が起こっている。加えて、パレスチナのガザに拠点を置くハマースは、ガザのムスリム同胞団から生まれた、武力闘争をもっぱらとする別働隊なのだ。その頑強さは日本の新聞を通じても、知ることが出来よう。
そして誰もが知っているウサーマ・ビン・ラーデン氏は、サウジアラビアの大学でムスリム同胞団の教授について、イスラムを勉強した人物なのだ。ムスリム同胞団にそのことを質した場合、彼らは全く別の組織だと返答するだろう。
しかしそうだろうか、組織が長期的に存在し、しかも拡大するためには鉄の結束が必要なのだ。それ無しには組織はばらばらになり、何時の間にか消えてしまおう。それは敬虔なイスラム教徒の結束する組織だから生き残れる、という説明も成り立とうが、それだけではあるまい。
メンバーの信仰心、メンバー内の厳しい規律、敵に対する憎しみ、組織のゴール、などが一体となって、それを可能にしているのではないのか。それが地下に潜行してなお、組織が生き残っていける、エネルギー源ではないのか。
こう考えてみると、ムスリム同胞団とは極めて共産党組織に、似た組織ではないかと思われる。共産党が組織として長期間存在しえたのは、鉄の規律があり、明確な敵が存在し、明確な綱領、明確なゴールがあったからであろう。そのため、メンバーはどんな厳しい状況に置かれても、くじけることなくその精神を維持できたのではないか。
それではムスリム同胞団が権力を掌中にしたとき、何が起こるのであろうか。それは彼らの認識にそった、厳しいイスラム法(シャリーア)の徹底ではないのか。
イスラム教は本来許しの宗教なのだが、明確なイスラム法(シャリーア)が存在するために、イスラム教が内包している許しや、寛容さは表面に出難い。厳格なイスラム教徒はどちらかと言えば、頑迷なまでにイスラム法(シャリーア)に則って、政治を司ることを選択するだろう。
ムスリム同胞団が今回の選挙を前に、コプト教徒との共存や、女性の権利などに関する立場を麗々しく披露したが、それは戦術ではあっても戦略ではない。
そのことに付いて一番分かりやすい質問をするとすれば『名誉の殺人』について彼らがどのような見解を持っているのか、実際にどう対応するのかを問えば分かろう。ムスリム同胞団は多分に名誉の殺人に対し、黙認や許容の立場を採るのではないかと懸念される。
もう一つのムスリム同胞団の危険性は、エジプトで与党になった場合、リビアやシリア、ヨルダンなど、他の国々のムスリム同胞団の反体制活動を、支援するようになるということだ。ムスリム同胞団には国境は無いのだ。
もちろん、ガザのハマースに対する支援も、活発になっていくと思われる。その場合、エジプトはいやおう無しに、イスラエルとの戦争に突入していくことになろう。あるいは良くても戦争の一歩手前まで、緊張した関係にならざるを得ないということだ。それは中東全体の平和と安定を破壊することになる、危険なものなのだ。
注:名誉の殺人とは家族の女性が不倫、不純行為に走った場合、あるいはそう疑われた場合に、女性の家族が家の名誉を守るために、彼女を殺害する行為で、イスラム世界では多くの国で、黙認されている。