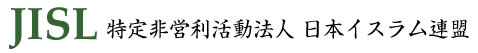日本財団の笹川陽平会長が、インド、エジプト、レバノンを訪問し、ハンセン病施設を訪問することになり、訪問先にアラブの国が含まれているということから、私にも同行の誘いをいただいた。
笹川陽平会長は一年のうちの半分以上を、ハンセン病対策で世界中を飛び回っている。年間の外国出張の回数は、常人では考えられないほど多い。帰国した当日に、再度外国に出張するということも、何度もあるようだ。
今回の出張も、深夜に現地に到着し、翌日早朝から行動開始という、ハード・スケジュールの連続だった。氏にそれを可能にしているのは、責任感と仕事への情熱なのであろう。
笹川陽平氏の各国のハンセン病施設への訪問のなかで、印象に残ったことを、少しだけご紹介しようと思う。氏はハンセン病に罹り、完治した人たちと手を握り、抱き合って激励していた。
エジプトのハンセン病罹病者の施設を、訪問し終えたとき、現地のテレビがインタビューをした。インタビュアーとのやりとりは、およそ次のようなものだった。
Q:貴方をこの病気の対策に駆り立てているのは何ですか?
A:ハンセン病に罹った人たちがどれほど苦しみ、完治後も苦しんでいるかを考えたとき、放置しておけないのです。あの人たちの手も私の手も暖かい。同じ人間の血が流れているのです。しかし、彼らと社会との間には、厚い高い隔壁があるのです。それを取り払わなければ、彼らを救ったことにはなりません。
Q:ここの施設をご覧になった印象どうでしたか?
A:素晴らしい、の一語に尽きます。しかし、そうであればあるほど、私には悲しく感じられました。ここにいる人たちには、家族がいます。病気が治った彼らは、素晴らしい施設ではなく、家族とともに過すべきなのです。
しかし、家族は彼らが帰宅することを、望んではいません。それは社会が彼らを、差別しているからです。社会が彼らを差別しなくなれば、家族は彼らを温かく迎えることが、出来るでしょう。
世界ではほとんどのハンセン病患者が、完治しているにも関わらず、彼らに対する差別は、相変わらず続いています。私は彼らが家族とともに暮らすことが出来、社会に復帰することが出来るようになるまで、活動を続けます。仕事が出来、普通に生活できるようになるまで。
この施設の少年は、もうハンセン病から解放されていた(完治していた)にもかかわらず、施設に住み続けていた。少年は「ここにいると楽しい、お兄ちゃんも一緒だから、寂しくないんだ。うちには帰りたくない。」と言っていた。社会の差別の壁が、いまだにこの少年の前に、立ちはだかっているのだ。
笹川陽平氏はインドの施設では、そこの老若罹病者の間に座り、抱き寄せていた。もちろんその人たちの中には、いまだに完治していない人たちが、いた可能性はあろう。そのときの笹川陽平氏の笑顔が、仏様のように高貴に見えた。
そのことを氏に告げると「若い女の人たちに囲まれるのは、誰だってうれしいさ。」と照れ隠しでお答えくださった。正直なところ、私にはそれほどの人類愛は、無いような気がして、後ろめたかった。
今回の笹川陽平氏との出張を通じて、一人の人間が自分の生涯をかけてやる仕事、その仕事と向かい合うということが、どのようなことなのかを教わった。以前、ある日本の国際的に有名な人権活動家が、エチオピアの難民キャンプを訪問したときの話を、聞いたことがある。
その人は難民の子供を抱き上げたのはいいのだが、テレビカメラの撮影が終わり、彼らのそばを離れた途端に、大慌てで自分の衣服に付いたゴミを、手で払い落としていたということだった。その人と比べると、笹川陽平氏のハンセン病への取り組みが、如何に真摯なものであるかが伺えよう。
世に言われる人類愛、人道、難民救済と幾つもの言葉を耳にするが、そのほとんどは、実は見せ掛けでしかないのではないのか。