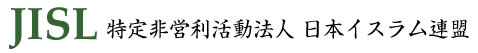イギリスのロカビー上空でパンナム機が爆発し、270人を越える犠牲者が出るという事件が起こったのは、1988年のことであり、もうだいぶ前の話になる。
事件後、イギリスやアメリカは犯行がリビアによって行われた、として幾つもの証拠を提示し、最終的に2人のリビア人を、事件の実行犯だとして逮捕した。逮捕に至るまでの間には、リビアとアメリカ・イギリスの間で、長い期間に渡って交渉が行われた。
述べるまでもないが、交渉とはアメリカとイギリスによる、リビアに対する脅しだった。その脅しと経済制裁によって、ついにカダフィ大佐がメグラヒ容疑者の部族を説得し、引渡しをすることになった。
部族との交渉に失敗し、それでも容疑者を引き渡すことになれば、カダフィ大佐の安全がリビア人によって、危険にさらされることになるからだった。つまり、当時カダフィ大佐はアメリカ・イギリスと、リビアの部族との間で、板ばさみ状態になっていたのだ。
容疑者を引き渡し、犠牲者の遺族に金を渡すと、アメリカもイギリスも手の裏を返したように、リビアに対し接近し、微笑外交を展開し始めた。それもそのはずだ。リビアは経済制裁を受けている間(パンナム機墜落事件以前から制裁は始まっていた)、インフラ整備、石油施設の老朽化に対する整備が出来ないでいたのだ。
したがって、制裁解除後のリビアは、まさにビジネスの大きな山が、幾つも転がっている状態の国だったのだ。
今年の夏になり、その微笑外交に拍車がかかった。容疑者メグラヒが許されていなかった「証言の機会を与える」という判断を、スコットランドの裁判所が下したのだ。
パンナム機の爆破事件をめぐっては、「麻薬取引がらみ」、「イランの報復」と幾つもの説が飛び交い、実行犯はパレスチナ・テロ組織だという説が出ていたが、ここに来てイランの報復説を、アメリカとイギリスは再度引き出そうというのであろうか。
もしそうだとすれば、実に見えすいた「イラン悪玉世論」の構築強化方法ではないのか。リビアが犯人ではなくイランだとするならば、リビアに対しアメリカやイギリスはどうわびるつもりなのだろうか、、またリビアが遺族に支払った金は返すというのだろうか。
事件後、イギリスやアメリカは犯行がリビアによって行われた、として幾つもの証拠を提示し、最終的に2人のリビア人を、事件の実行犯だとして逮捕した。逮捕に至るまでの間には、リビアとアメリカ・イギリスの間で、長い期間に渡って交渉が行われた。
述べるまでもないが、交渉とはアメリカとイギリスによる、リビアに対する脅しだった。その脅しと経済制裁によって、ついにカダフィ大佐がメグラヒ容疑者の部族を説得し、引渡しをすることになった。
部族との交渉に失敗し、それでも容疑者を引き渡すことになれば、カダフィ大佐の安全がリビア人によって、危険にさらされることになるからだった。つまり、当時カダフィ大佐はアメリカ・イギリスと、リビアの部族との間で、板ばさみ状態になっていたのだ。
容疑者を引き渡し、犠牲者の遺族に金を渡すと、アメリカもイギリスも手の裏を返したように、リビアに対し接近し、微笑外交を展開し始めた。それもそのはずだ。リビアは経済制裁を受けている間(パンナム機墜落事件以前から制裁は始まっていた)、インフラ整備、石油施設の老朽化に対する整備が出来ないでいたのだ。
したがって、制裁解除後のリビアは、まさにビジネスの大きな山が、幾つも転がっている状態の国だったのだ。
今年の夏になり、その微笑外交に拍車がかかった。容疑者メグラヒが許されていなかった「証言の機会を与える」という判断を、スコットランドの裁判所が下したのだ。
パンナム機の爆破事件をめぐっては、「麻薬取引がらみ」、「イランの報復」と幾つもの説が飛び交い、実行犯はパレスチナ・テロ組織だという説が出ていたが、ここに来てイランの報復説を、アメリカとイギリスは再度引き出そうというのであろうか。
もしそうだとすれば、実に見えすいた「イラン悪玉世論」の構築強化方法ではないのか。リビアが犯人ではなくイランだとするならば、リビアに対しアメリカやイギリスはどうわびるつもりなのだろうか、、またリビアが遺族に支払った金は返すというのだろうか。